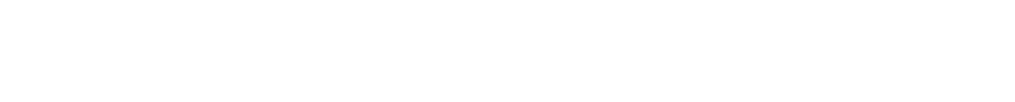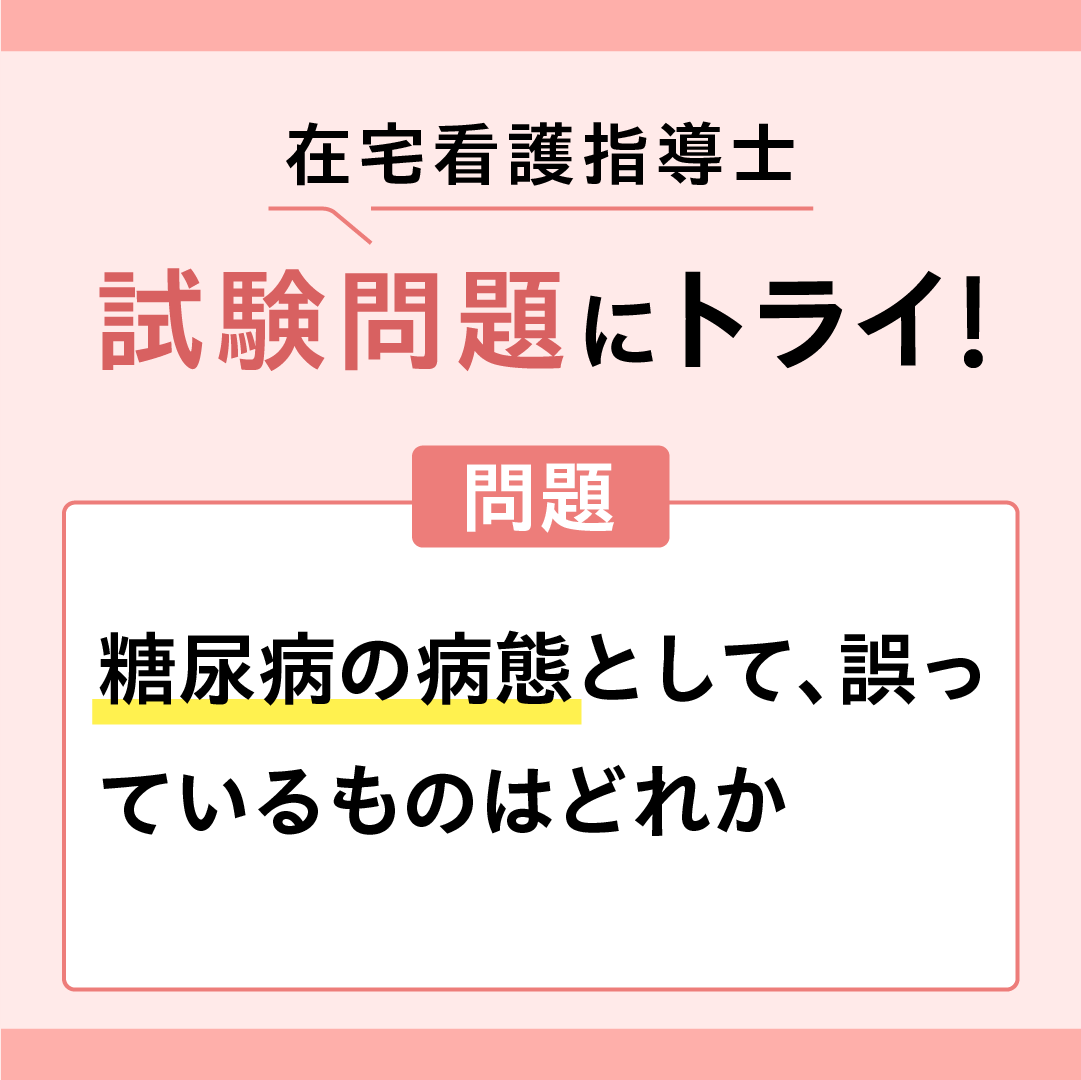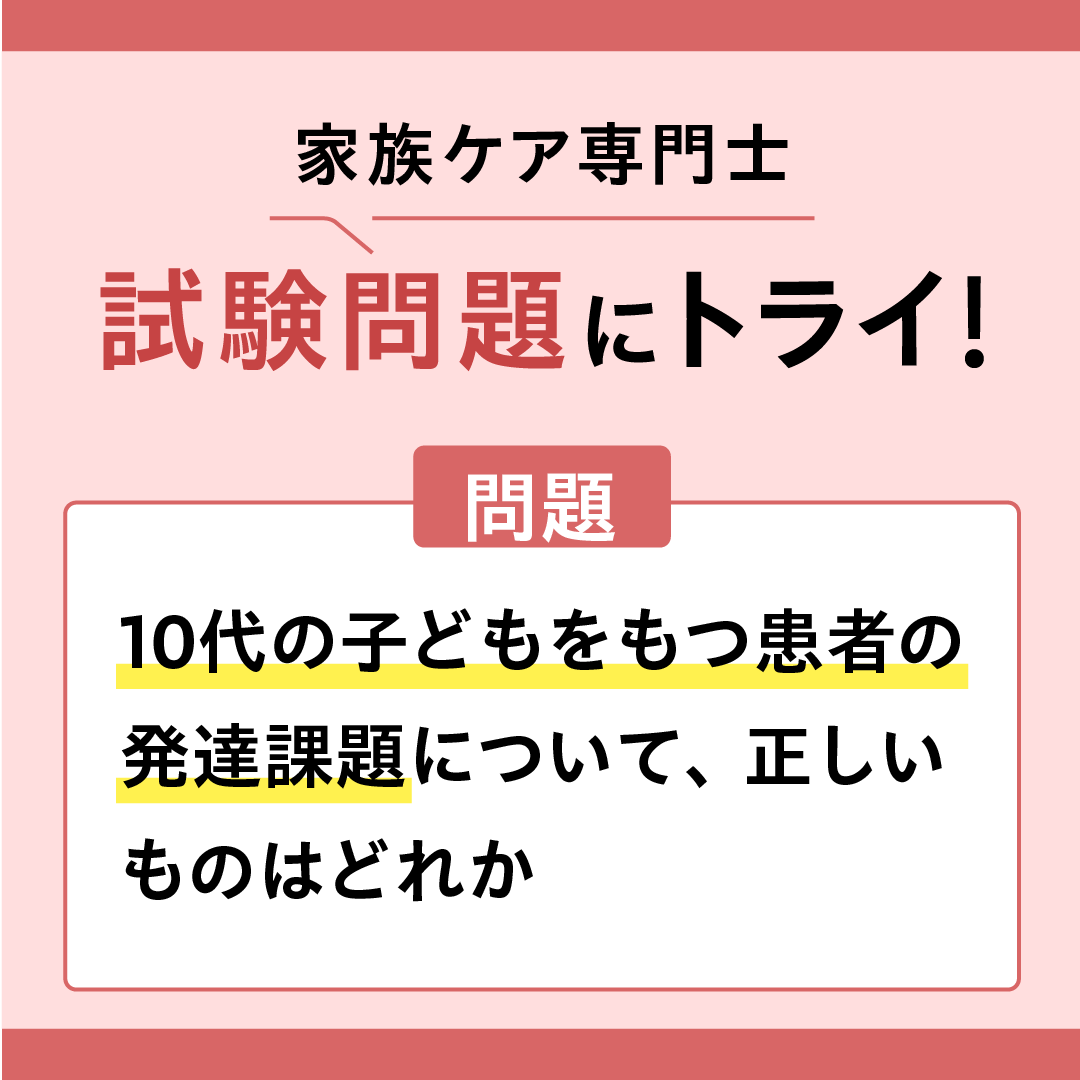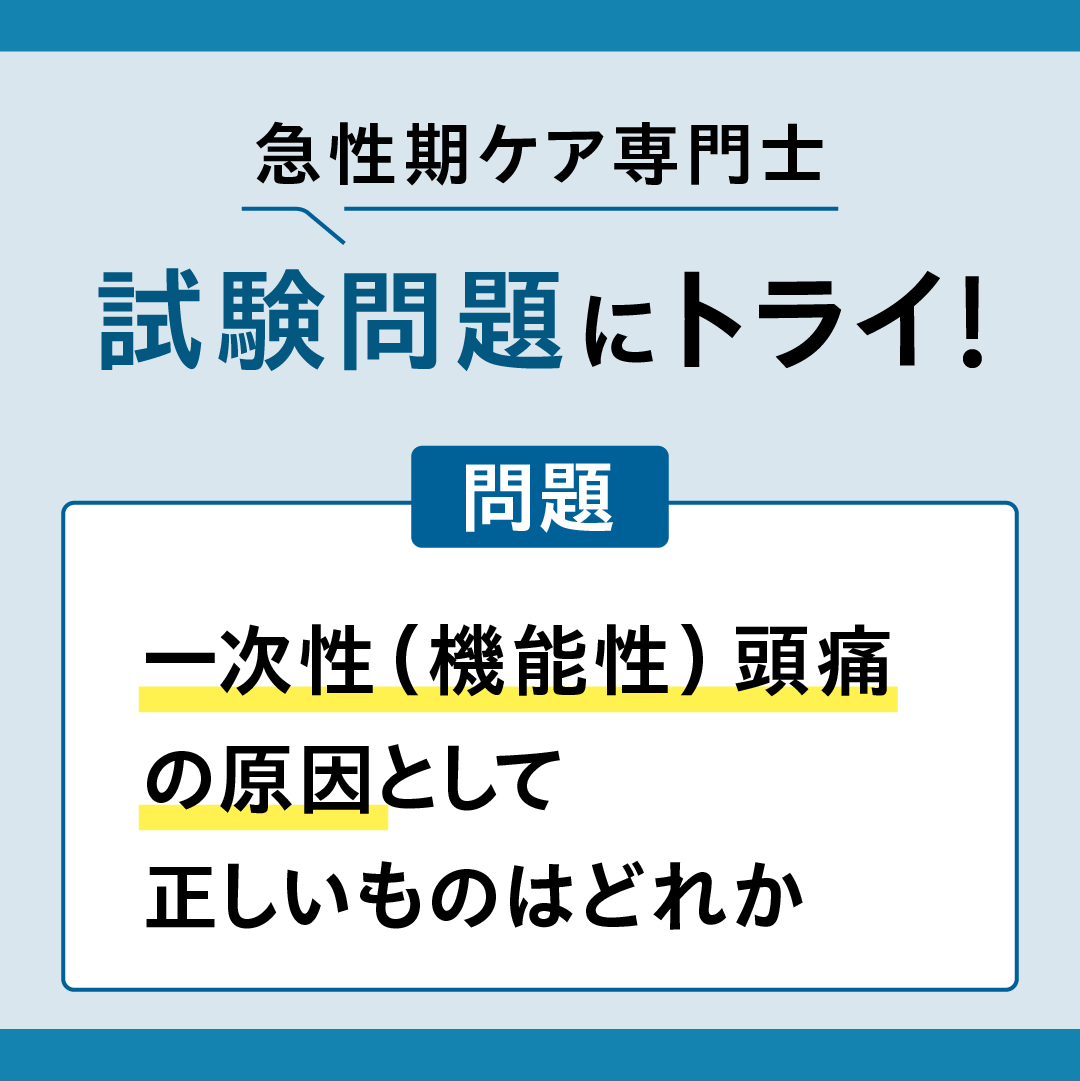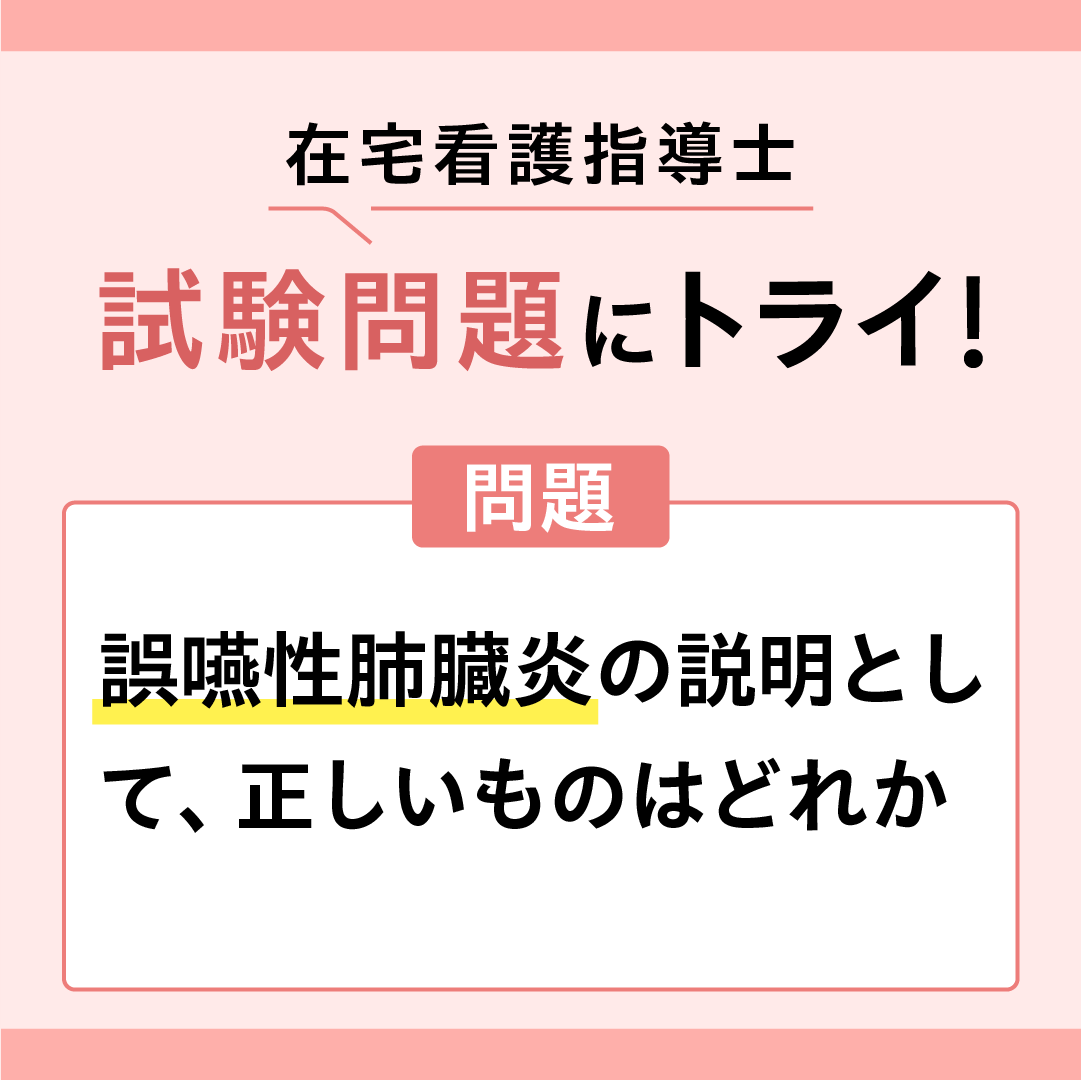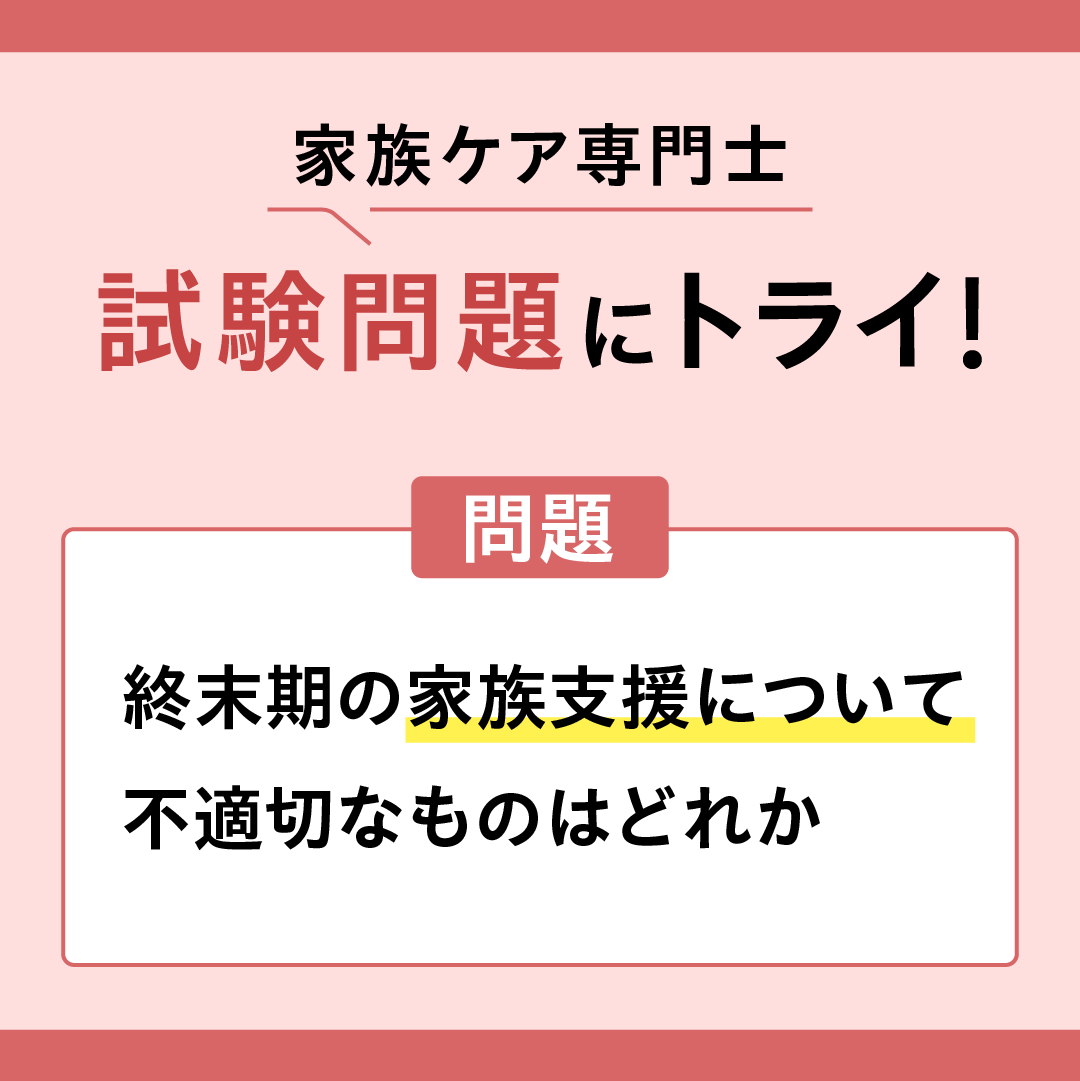- 目次
はじめに
「お母さんが死んだらどうしよう」という恐怖が小学生の頃からあります。
ありえない“たられば”ではなくて、私が妥当に長生きすれば、その年の差から考えて現実になるでしょう。
もうひとつ、同じ頃に抱いていた懸念が「お母さんが死んだとき自分は泣けるのか?」です。
「血も涙もない」という言葉があるように、お葬式で泣かない人が「冷たい人だ」と思われる場面はドラマでも漫画でもよく見られますし、泣く必要があるんだろうなと子供心に思っていたのかもしれません。
母と仲が悪いわけではないし、それどころか母のことは大好きですが、ぼんやりとしたこの懸念は大人になった今でも心の片隅にあります。
実際の看取りの現場でも、すべてのご家族が涙を流すわけではないでしょう。彼ら彼女らを目にしたとき、皆さんはどう感じているでしょうか。
今回紹介するカミュの小説『異邦人』は、まさに「母の死で泣かなかった人」の物語です。
1942年のフランスで発表されたこの一本の短編小説は、日本の小学生であった私にも、日々看取りの現場に臨む皆さんにも通ずることを綴っています。
「きょう、ママンが死んだ。もしかすると、昨日かも知れないが」という衝撃的な書き出しから始まるこの話は、母を亡くした主人公・ムルソーの生活を追った短編小説です。
手元の文庫本の裏表紙にあるあらすじを載せてみましょう。
母の死の翌日海水浴に行き、女と関係を結び、映画をみて笑いころげ、友人の女出入りに関係して人を殺害し、動機について「太陽のせい」と答える。判決は死刑であった(…)通常の論理的な一貫性が失われている男ムルソー(…)
「母親が死んだのに遊んでいて、意味もなく人を殺めて、死刑になっても反省すらしない」という、この作品が好きな私ですら「やな主人公だな~」と感じるあらすじです。
しかし実際に本編を読んでみると、そこまで理解を拒む主人公ではありません。
どういうことか? さっそく中身を見てみましょう。
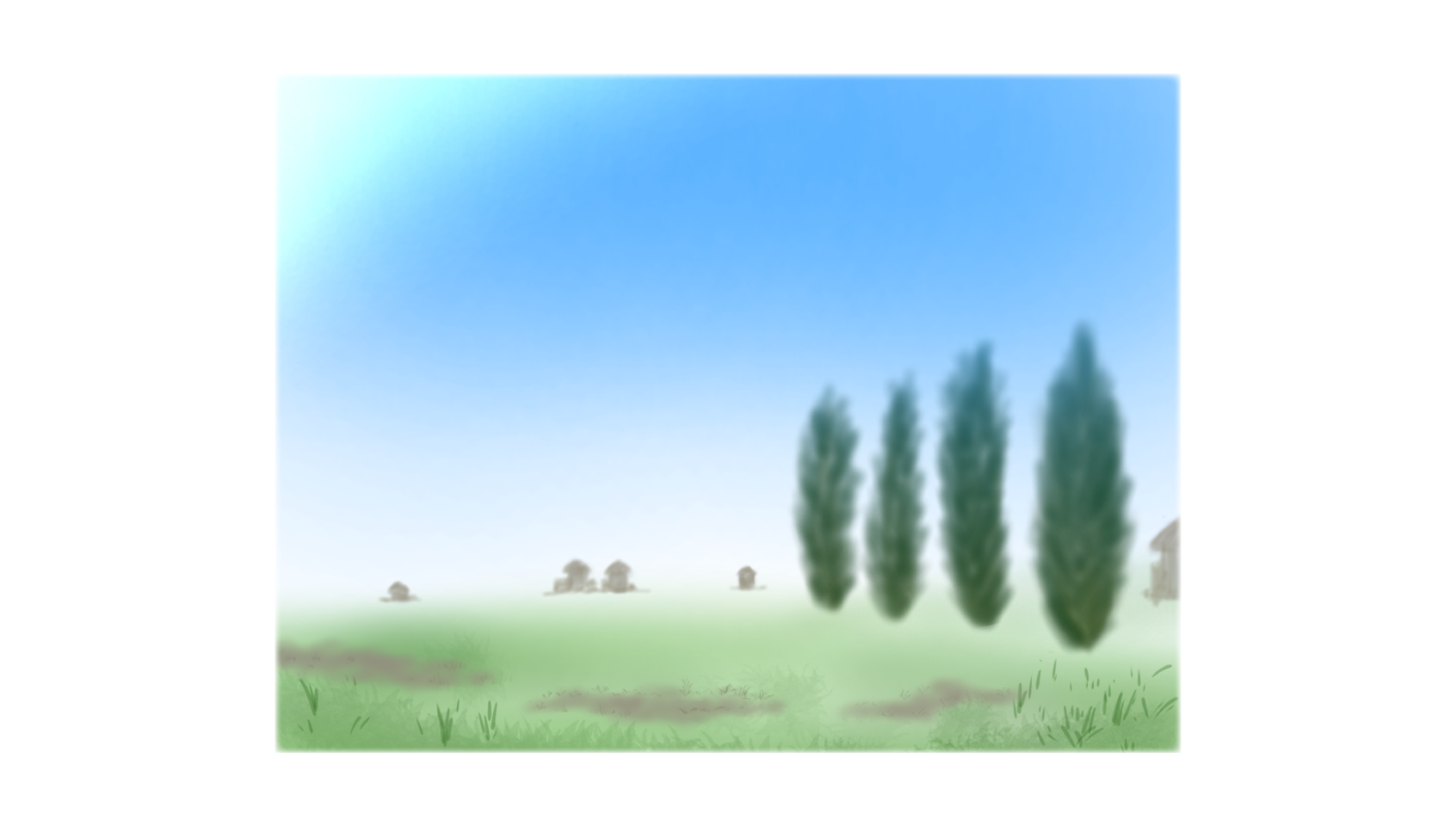
『異邦人』の物語
そもそもムルソーはなぜ母の命日すら「もしかすると、昨日かも知れない」なんてぼんやりしているのかというと、それは彼の「ママン」が養老院…今でいう老人ホームで暮らしていたからです。
「ハハウエノシヲイタム、マイソウアス(母上の死を悼む、埋葬明日)」という電報を受け取ったムルソーは、母が亡くなった日も分からないまま、仕事の休みを取ってその養老院に向かうことになります。
式の間じゅう、養老院で母と知り合った恋人や友人が泣きながらその死を悼む中、ムルソーは涙を流さずにいました。
「人並みに悲しむそぶりを見せなかった」、彼はこのせいでどんどんと窮地に陥ってしまいます。
ムルソーはあるとき、トラブルに巻き込まれて、武器を持った一人の男を殺害してしまいます。
はじめは誰もが、すぐに放免になるだろうと気にしていませんでした。
しかしこの事件の裁判において、論点がだんだんと殺人事件から「過去、母の埋葬に際して泣かなかったこと」にすり替わっていくのです。
私の弁護士は、たまりかねて、(…)「要するに、彼は母親を埋葬したことで告発されたのでしょうか、それとも一人の男を殺害したことで告発されたのでしょうか?」傍聴人は笑い出した。しかし検事はふたたび立って、(…)「しかり、重罪人のこころをもって、母を埋葬したがゆえに、私はあの男を弾劾※するのです」と、彼は心をこめて叫んだ。この言明は、傍聴席に対して著しい効果を与えたように見えた。
※弾劾(だんがい)……罪状を調べ、あかるみに出すこと。
裁判の結果、ムルソーは「精神的に母を殺害した男」とまでされて、死刑を言い渡されてしまいます。
ムルソーは極悪人か?
ムルソーが本当にこの裁判で言われるような極悪人で、母を愛していなかったかというとそんなことはありません。
実際に彼の口から「私は深くママンを愛していた」と語られますし、埋葬にあたって次のように母へ思いを馳せてもいます。
しばしば母とペレーズ氏※は、夕方、看護婦に付き添われて、村まで散歩に出た、と院長はいった。私は自分の周囲の野原をながめた。空に近く、丘々まで連なる糸杉の並木、このこげ茶と緑の大地、くっきりと描き出された、まばらな人家——これらを通して、私はママンを理解した。夕暮れは、この地方では、憂愁に満ちた休息の一刻にちがいない。
※ペレーズ氏……ムルソーの母の養老院における恋人。周りからは許嫁だとまで言われていた。
にもかかわらずムルソーが死刑にまで追い込まれたのは、社会的に正しいとされる悲しみ方ができなかったから、と言えます。
裁判や死刑となると話は大きくなり過ぎますが、私たちの暮らす社会にも存在する「ちゃんと死を悼む」という“正しさ”は、これを読む皆さんにも心当たりがあるのではないでしょうか。
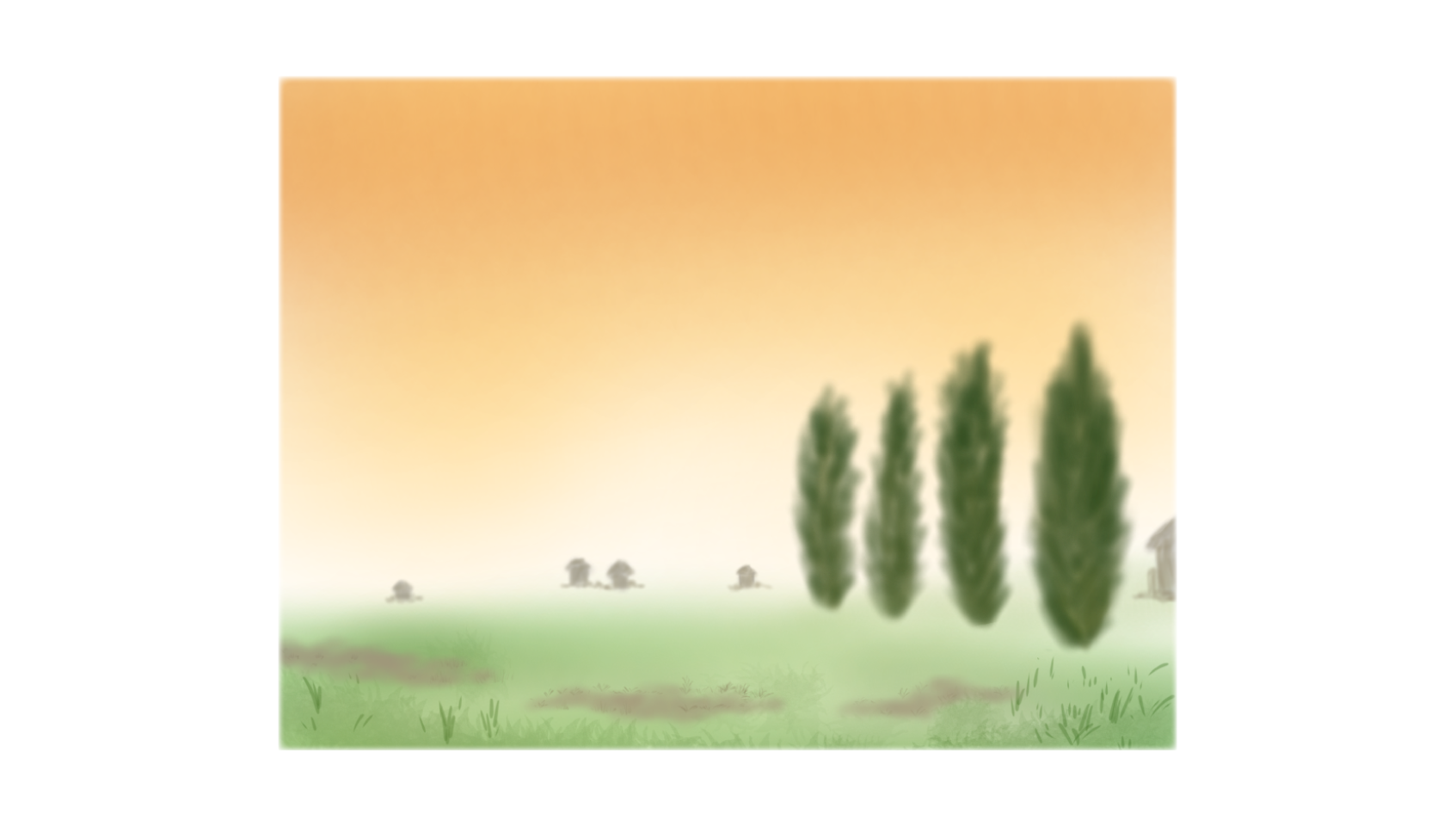
自分なりに死を悼むこと
人の死を悼むということはどういうことなのか?
形式通りに式を進め、涙を流し、何も喉を通らない……という状態にならなければ、故人を愛していないし、死を悼んでいないことになるのでしょうか?
もちろん伝統的な形式には、その歴史の重みの分だけ旅立つ人々への思いやりが積もっています。
しかし、生きている人が誰一人同じでないように、亡くなった人も誰一人同じではなく、見送る人も関係性だって、すべて同じではありません。
正しい死の悼み方などなく、葬式で泣かなかったとしても、自分なりに故人を想い、思いやること。それこそが、死を悼み、向き合うことではないでしょうか。
今回取り上げたお話は、この作品の魅力のほんの一部です。むずかしい小説ですが、ぜひ手にとっていただき、皆さんの日々のお仕事や生活の潤いにしてもらえたらうれしく思います。
最後に私の好きな一節を紹介して終わりにしたいと思います。小説の終わり、ムルソーが自身の死刑を独房で待っている場面です。
一つの生涯のおわりに、なぜママンが「許嫁」を持ったのか、また、生涯をやり直す振りをしたのか、それが今わかるような気がした。あそこ、幾つもの生命が消えてゆくあの養老院のまわりでもまた、夕暮れは憂愁に満ちた休息のひとときだった。死に近づいて、ママンはあそこで解放を感じ、全く生きかえるのを感じたに違いなかった。何人も、何人といえども、ママンのことを泣く権利はない。
※引用はすべてアルベール・カミュ著 窪田啓作訳『異邦人』(新潮社、1954年)による。また注及び太字、省略はすべて稿者による。
終末期ケア専門士とは
終末期ケア専門士は、「臨床ケア」におけるスペシャリストです。
患者・利用者様の一番近くで「支える人」として、エビデンスに基づいたケアの実践をおこなえることを目指します。
「終末期ケア」のスペシャリストを目指す人にとって、ぴったりな資格です!

公式テキスト 販売中

アステッキでは、終末期ケア専門士公式テキストを販売しております。
学びの意欲を持ち続ける終末期領域のみなさまにとってぴったりな一冊となっております。下記URLより詳細をご確認ください。
アステッキの教材なら「忙しいあなた」でも資格取得を目指せる。
アステッキの教材を利用した多くの方が資格試験に合格されています。
その理由は徹底した教材作りへのこだわりに隠されています。
あなたも知識の幅を増やしたり、就職の選択肢を広げたりと自身の可能性を広げてみませんか。